連載5回目です。前回まではこちら👇です。
医療の第一の目的は病気や怪我による身体的苦痛を取り除くことにあるはずだ。秋山の左手は医学的には何の異常もみられない。苦痛など存在するはずがない。苦痛は秋山の生み出した幻なのだ。この場合、手首を切断することよりも、それを切断したいと考えている秋山の精神面のケアが最も大切なことなのだ。彼の左手は救われなければならないし、治療を受けるべきは秋山の精神である。でも、果たして本当にそうなのだろうか。片岡は自分の考えに自信が持てなかった。
片岡の脳裏に由実子のことがまた浮かんできた。
由実子を自分の生活から切り捨てることと、秋山が自分の手首を切り捨てることとは似てはいないか?
え? 俺は一体、何を考えている? 由実子と手首を同じ次元で考えるなんて、どうかしてしまったんじゃないのか? 片岡は浮かんできたその考えをくしゃくしゃに丸めて消してしまおうとして、、、やめた。そして、もう一度考えてみた。
ちっぽけなたった一つの出来事が一生を左右してしまうことはよくあることだ。それどころか、一生を台無しにしてしまうこともよくあることだ。何度も繰り返し聞かされた父親との出会いを恨む母親の言葉から、片岡はそれを痛いほどよく承知していた。だが二人にとっての不幸は、その出会いにではなく、その別れにあったのかもしれない。人生の中で一瞬だけ楽な流れに身を任せてしまったことがその不幸を生んだのではないか。もう少し話し合えば、二人には違う流れが見えてきたかもしれない。由実子と別れるのは楽な方の流れに乗ることなのではないか。それに乗ってしまえば、きっとそのまま片岡の心の中の堤防が切れる。これまで堪えてきたものが一気に流れ出す。どれほどの澱みがそこから溢れてくるだろう。自分が自分でなくなってしまうかもしれない。
流れの先を見ることさえ出来れば、どちらに向かうべきか判断するのは難しくない。由実子と喧嘩した後でいつも思い浮かべる心象がある。それは陽あたりの良い庭で、犬とじゃれているよちよち歩きの孫の無邪気な様子を、お互いに歳をとった二人が穏やかに眺めている、そんな風景だった。そんな想像の世界に心を泳がせると、由実子の笑い声が聞こえ、片岡の脳裏に渦巻いていた暗い想いを消し去っていってくれる。そしてその後、片岡は何もなかった顔をして「旅行にでも行かない?」と由実子を誘ってみる。
切り捨てることではきっと何も解決しやしない。
「今のあなたにとってその左手は確かに、煩わしく不快な存在かもしれません。でもそのことが左手の存在を否定する理由にはなりません。その手がそこにある限り、きっといつかはあなたの意思を通じることが出来るはずです。切り捨ててしまえば、二度と元には戻らないのです。自分にとって嫌なものは何であれ、すべて消えてなくなればいいというのは、あまりに我がままな考えではありませんか」
「左手にだって生きる権利があるということですか、先生。それなら、私にだって生きる権利があります。私とこの左手のどちらが生きる資格がありますか」
「そうじゃない。相手を憎み、排除しようとするところからは何も生まれない。失ってから後悔しても、もうどうしようもないんだ……」
「理解し、認めようと努力するべきだと、先生はおっしゃりたいのでしょう。でも、そんなきれいごとですべての問題を解決できますか。いくら努力しても理解できないものもこの世の中にはたくさんあるのではありませんか。現に、長年連れ添った家内でも、こんな私の姿を見て逃げ出してしまいました。それでいいのです。逆の立場なら、私だってきっとそうしたでしょうから」
片岡は何も答えられなかった。
「この左手は私のものです。それをどう扱おうと私の勝手ではないですか。私は右利きです。左手がなくなったとしても、右手だけでなんとかなると思います。一日中私をさいなむ、この不快を消し去ることが出来るのなら、多少のリスクは厭いません。先生方はいろんな検査をされて、左手には何の異常も見当たらないとおっしゃるだけで、私の心の底からの訴えに耳を貸そうとはしてくださいません」
「ではご自分でおやりなさい。それを誰も止めることはできません。あなたがご自身で左手を切断されたなら、出血を止め、痛みを和らげる治療をいたしましょう」
二人とも感情的になっている。激しく言い合う二人の間で相変わらずゆらゆらと揺れる秋山の左手首だけが平常心を保っている。そんなふうに見えた。看護師が巻いた白い包帯のせいで、場違いなほどそれは落ち着いているように見える。
「医学的に診てあなたの左手首のどこにも異常はありません。考えられるのは手と脳をつなぐ神経系統のどこかに異常があるか、それともあなたの精神面の疲れによるものか、という二点です。この病院に来るまでに精神科の診察も受けられたかも知れませんが……」
潔癖症と言えるほどきれい好きだった秋山が、ある日最も秋山に親しい存在であるその妻から臭うと指摘された。果たして本当に臭ったのかどうかは別の話になるが、それが原因で秋山は手の臭いが病的に気になるようになった。妻や客に嫌われるのではないか、いやもうすでに嫌われているのではないか。疑心暗鬼になる。そしてついに秋山は自分は嫌われているのだと強烈に思い込んでしまった。ところが無意識のうちに、秋山の心を押しつぶそうとする負担をすり替える作業が頭の中のどこかで行われた。嫌われているのは自分ではなく、この左手なのだ。秋山はすべてを左手のせいにすることで自分を正当化した。そして最後に、左手を自分の身体から切り離してしまえばこの物語は完結する。
片岡の考えはそれでようやく腑に落ちた。でも、それを秋山に説明して一体何になる。
「狂っているとおっしゃりたいわけですね。確かにそうかも知れません。この左手を見れば誰だってそう思われるのが当然でしょう。でもこの左手の不快は確かに存在するのです。目に見えないもの、科学的に証明されていないものは信じないというあなたがたの方がおかしいのです。この手の異常が日増しにひどくなっていくのに、誰にも理解されない。そんな私の恐怖があなたにはお分かりいただけないでしょう」
秋山の眼窩の奥が滲んで見える。
「ここ数日ほとんど眠っていません。精神科の治療が効果あるものだとしても、もう我慢の限界を越えてしまいました。私の方から手首を切り落とさなければ、きっとこの手首が私を絞め殺してしまうでしょう」
ああ、そうだ。秋山の気持ちは、もうとっくに決まっている。これ以上の議論は何の意味も持たない。そう片岡は思った。
「秋山さん、あなたがおっしゃることの意味は理解できます。そしておそらく本当にあなたは左手に異常を感じておられるのだ思います。ところが医師としての私は、あなたのご希望に添うことは出来ませんし、そうすることが正しい判断だとは絶対に思えません。私に出来るのはあなたが不快を感じないように、麻酔注射を打ってあげることくらいです。ペインクリニックの技術はかなり進んでいますから、きっとそれに満足されると思いますが」
片岡はこれで妥協してくれるのではないかと微かな期待を込めて最終提案をしたのだが、秋山の表情は少しも変わらなかった。そしてさらに食い下がった。
「お金ならあります。店を売って残った金がここにあります。このままだと私は本当に狂ってしまうか、その前に自殺してしまうかもしれません。先生、私は死にたくありません。まだまだ一杯やりたいことが残っています。生きていたいんです。でもこのままでは、毎日が地獄のようです……。なんとかしていただけないでしょうか」
秋山はセカンドバッグを片岡の前に置くと、深々と頭を下げた。その中に秋山の全財産が入っているのだろう。バッグの上で左手首が相変わらず不自然な踊りを続けている。もうこれ以上何を話しても無駄だと片岡は悟った。
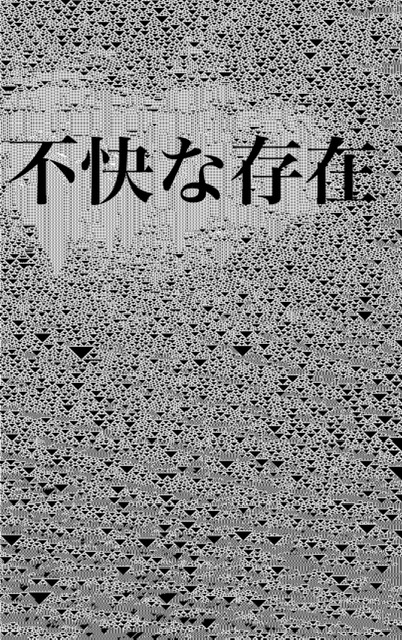
よければtwitterものぞいてみてくださいね。山猫 (@keystoneforest) | Twitter

山猫🐾@森の奥へ