連載6回目、最終回です。前回まではこちら👇です。
秋山はセカンドバッグを片岡の前に置くと、深々と頭を下げた。その中に秋山の全財産が入っているのだろう。バッグの上で左手首が相変わらず不自然な踊りを続けている。もうこれ以上何を話しても無駄だと片岡は悟った。
「Sという医者がY市にいます。お金はかかりますが、きっとあなたのご希望通りの治療をしてくれるはずです」
短い沈黙の後、片岡は秋山の左手首に向かってそう告げた。
診察室から出ていく秋山の後ろ姿に向かって「お大事に」とはさすがに言えなかった。
何事においてもくよくよ考え込んでしまうのが片岡の悪い癖だった。見方を変えれば、いつも反省を怠らない謙虚な態度であるとも言えるのだが、由実子が善意に解釈してくれない以上悪い癖なのに違いなかった。
S医師を紹介するなんて、お前はどうかしている。自分の手さえ汚れず、自分に見えないところでならどんなことが起きようと関係がない。そう思っているのか。なんて卑怯な人間なんだ、お前は。
片岡はいつまでもぐずぐずと考えていた。そして由実子のことも心の底で燻り続けている。
朝から片岡はずっと「離婚」を考えていた。由実子の存在が自分に不快を味わわせるのであれば、別れてしまうしか残された道はない。それをあれこれ考えている。これまで離婚を思い止まらせていたのは、母親の呪縛のせいだったかもしれない。
「あなたの父親のような人間には絶対になるんじゃない」
好きになった人なら、一緒に暮らそうと思った人のことなら、生涯愛し続けなさい。母親の声がいつまでの片岡の心を縛っている。
もしかすると、母親は最後まで父親のことを愛していたのかもしれない。片岡自身に注がれた愛情は、本当は父親に向けられたものだったのかもしれない。片岡は親子三人が最後に会った時のあの母親の目を思い出した。あの目の光は一体何を訴えていたのだろう。あれ以来、何度か片岡を父親に会いに行かせたのは、自分の存在を忘れないで欲しいという母親の願いがあったからかもしれない。かつて一緒に暮らした自分の存在を、片岡に会わせることで思い出させようとしたのかもしれない。母親は最後まで父親を愛していたのかもしれない。戻ってきて欲しいと願っていたのかもしれない。離婚の後、母親が誰にも心を開かなかったのは、父親と一緒に暮らした頃の自分のままで時間を止めてしまいたかったからかもしれない。
他の人を愛するということは、かつて愛した人と過ごした自分の時間を否定することになる。そして、それは過去の自分自身を切り捨てることになるのかもしれない。そんな思いが片岡の心に浮かんできた。
片岡は由実子を愛していた。本当は我がままで気の強い由実子が好きだった。今の二人の間にある溝は、由実子が存在しなくなることで消え去るが、埋める努力を続けることによってもいつかはきっとなくなる。溝を埋めるためにはもっともっと由実子と話し合う時間が必要だ。
長い診察がようやく終わった。時刻はもう四時を過ぎていた。その日は勝手に外で食事してくるからと、その朝、由実子は喧嘩腰に言っていた。でも、この時間なら由実子はきっとまだ家にいるはずだ。
片岡は急いで帰宅した。家のどこにも由実子の姿はなかった。
帰宅した片岡を待っていたのは、ダイニングテーブルの上に置いてあった自分あての封筒だった。中には離婚届が入っていた。それだけだった。
手首に私が絞め殺される、秋山はそう言って片岡にすがった。片岡にとって由実子はどんなに不快でも切り落とせない存在だった。ところが由実子は片岡をあっさりと切り落としてしまった。由実子にとって片岡はたったそれだけの存在でしかなかったのだ。
手首に殺された。
切り落とされそうになった手首が、切り落とそうとした男の首を締めて殺した。殺された男は片岡自身だった。
*
一カ月ほど経ったある日、片岡は秋山から電話を受けた。
S医師は秋山の希望をすぐに叶えてくれたということだった。そして、秋山を苦しめ続けた不快感はすっかりなくなってしまった。もちろん切断した跡の痛みはまだ残ってはいるが、以前に比べればすっかり楽になったらしい。あれ以来ゆっくり眠ることができるし、これほど気持ちが晴れ晴れとしたのは久しぶりだと電話口の向こうで秋山の声がしている。だが、話の内容ほどに秋山の口ぶりは嬉しそうではない。もう秋山のことは忘れてしまいたいのに、わざわざ電話をかけてきたことに片岡は少し腹を立てた。
「ところが、、、」
秋山は一度話を区切って、また感情を押し殺したような声で話を続けた。
「、、、つい先ほどのことです、先生。こんなことって、、、こんなことになるなんて、信じられますか?」
秋山はそこでまた言葉を切り、短く笑ったような声を立てた。
「、、、また臭ってきたのです。前とまったく同じ臭いがするのです。いえいえ、左手はもう切りましたからそれではありません。今度は右手が臭うのです。この話をさきほどS医師にいたしましたところ、とてもご気分を悪くされたようで、もうこれ以上は私のことに付き合えないと取りつく島もないのです。先生、本当に申し訳ありませんが、、、」
片岡は受話器から耳を放した。それ以上聞きたくなかった。それでも電話口から秋山の声が追いかけてくる。
「、、、S医師以外にお心当たりはありませんでしょうか。そうです。もちろん今度は、右手を切り落としてくれるお医者さんです」
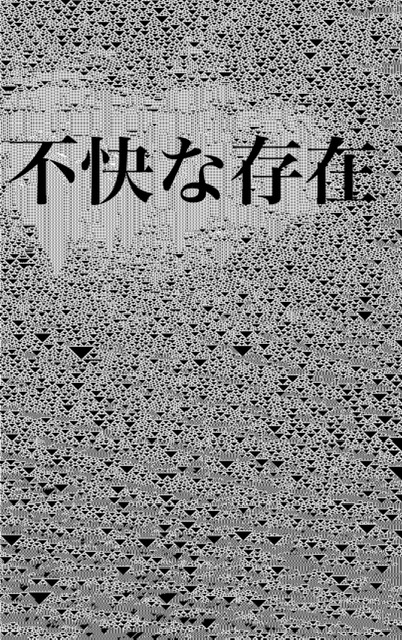
よければtwitterものぞいてみてくださいね。山猫 (@keystoneforest) | Twitter

山猫🐾@森の奥へ