順番待ちの外来患者が、ようやく片手で数えられるほどになっていた。お昼で終了するはずの診察時間はもうすでに二時間は超過している。昼食を昼にとれないのはいつものことだが、その日の片岡にはかなりこたえていた。
要領を得ない老人との面談にも気長に付き合えることで評判の片岡だったが、その日は自分でも驚くほど厳しい口調で患者に接していた。その日の朝、妻の由実子と言い争ったことが片岡から患者を気遣う余裕を奪ってしまっていた。と言っても、言い争いはその日だけのことではなかったけれど。
かなり前から由実子の片岡に対する感情は冷め切っていた。振り返ってみれば、二人が結婚してから三年間、互いを結ぶ感情が愛情だったことなどほとんどなかった。露骨に相手を傷つける言葉を投げあうようになったのは最近になってからだが、結婚当初からすでに感情のすれ違いは随所にあった。三年間別れないできたのは自分の辛抱強さによると片岡は思っていた。そして辛抱強さが必ずしもよい結果を生むとは限らないとも思っていた。片岡から見れば、由実子ほど我がままな女はいない。由実子にとって結婚相手は医者でありさえすればそれでよかった。医者としての肩書を夫になる男性に求めただけで、それ以上は何も必要ではなかった。由実子は医者の夫人という座に憧れていただけなのだ。ところが実際に医者である片岡と結婚生活を始めてみると、案外そこは居心地の悪いところだと知ったのだろう。それはおそらく互いの努力不足がもたらした結果には違いなかったが、由実子はそれをすべて片岡のせいにすることで自分の気持ちを支えようとしている。片岡はそう考えていた。
これまで何度か頭に浮かんでは消し去っていた「離婚」を真剣に考える時が来たようだ。片岡は午前の診察中ずっとそんなことを考えていた。なのに、それでもまだ時間をかけて話し合えば何とかなるのではないかと、期待を抱いてしまうところが片岡の悪い癖だった。由実子と衝突するたびにその癖を攻撃材料にされる。
「どうしてそんなに優柔不断なの? ホントにあなたって決断力ない人ね」
その日の朝も由実子は甲高い声で片岡を罵った。
由実子のことを考えると苛々してどうしようもなかった。とにかく少しでも早く仕事を済ませてしまいたかった。かと言って、仕事を終わらせても、とりたててすることなどなかった。パチンコもアルコールも片岡の興味を惹く存在ではなかった。ただ中途半端な気持ちのままで仕事をするのが嫌だっただけだ。朝の諍いの原因がなんだったのか、片岡にはもう思い出せない。おそらくそれは寝起きの悪さが許せないと言う類のことだったに違いない。二人が一緒にいること自体がおそらく間違いなのだろう。
*
残りの患者は三人、あと三〇分だと片岡は見当をつけた。その男さえやってこなければ、三〇分どころかおそらく一〇分後には帰り支度に取りかかることが出来ていただろう。
その男は秋山和弘、五八歳、訴えは「手の不快感」と問診表にあった。名前に覚えはなかった。おそらく初診の患者だ。整形外科担当である片岡の診察室の前では、ギブスを巻いた足を引き摺っている男や腰の痛みを訴える女が順番を待っている。
「秋山さん」と呼ばれて待合室の椅子から立ち上がったのはひょろりと背の高い男だった。左手にだけ大きな手袋をはめている。炊事用ゴム手袋のようだ。ギブスや包帯を巻いた人間が大半を占める待合室で、そのゴム手袋はあまり目立つ存在ではなかったが、病院へやってくるまでは多くの人の視線を集めたであろうと容易に想像できた。
初診の患者を診る時、まずその人の表情をじっくり見るところから診察は始まる。ボサボサ頭と眼窩の深い窪みとが秋山の心の翳を象徴しているようだ。おそらくかなりの睡眠不足なのだろう。「不快感」があるのは手袋をしている左手だと思われた。まずは手袋を脱がせるところから始めよう。
「どうしました。秋山さん」
片岡は穏やかに声をかけた。それには答えず、秋山は手袋をはめた左手をゆっくりと片岡の方に差し出した。
「臭いませんか、先生。私の手、変な臭いがしませんか」
秋山の手は片岡のすぐ目の前にあった。ピンク色の手袋は甲の部分に擦られたような筋が何本か走っている。ゴム特有の臭い以外は特段何も臭わなかった。秋山は続けて言った。
「これを切り落として欲しいのです」
低い声だったが、ふざけた口調ではなかった。秋山の眼窩の奥の黄色く濁った白目がどろりと揺れた。
「これって……あなたの手のことでしょうか」
片岡は思わず問い返していた。どんな場合にも平常心で臨むのが、患者の信頼を得る最短の道だと信じているのだが、その時の片岡は動揺の色を隠しきれなかった。気持ちを落ち着かせるためにするいつもの癖で、煙草を吸うようなふりをしてボールペンを口にくわえ、片岡はもう一度ゆっくりと男を観察しなおした。真剣なのか、ふざけているのか、それとも狂っているのか、その表情からは判断がつかなかった。
「このことをお願いしますのは先生で六人目になります。どの先生も私の話を真剣にとりあってはくださいませんでした。検査の繰り返しばかりで、異常なしと言う結果が出ると、私を適当に追い払うのです」
秋山が片岡の前に差し出した手は、不自然な向きに手首を曲げたまま肘から先がゆらゆらと揺れている。
「秋山さん、お伺いしましょう。ゆっくりと最初からお話しください」
とりあえず話を聞くしかないだろう。片岡は覚悟を決めた。「長い話になりますが」と前置きすると、秋山は感情を抑えた口調で静かに話し始めた。
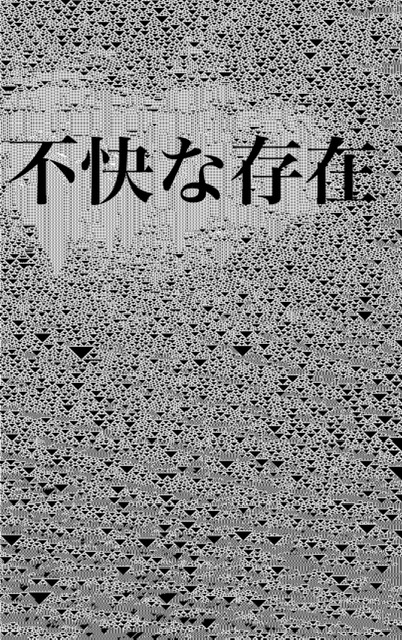
よければtwitterものぞいてみてくださいね。山猫 (@keystoneforest) | Twitter

山猫🐾@森の奥へ