連載4回目です。前回まではこちら👇です。
秋山の診察にいつまでかかるか見当もつかなかった。もうすでに一時間以上秋山の話は続いている。
残りの患者の診察を終え、時刻を確かめようとして、片岡は由実子とのことをふと思い出した。
とたんに一層憂鬱な気分に落ちていった。胸が苦しくなる。憂鬱は心臓で味わうのだと片岡は思った。普段感じない心臓の存在を、気分がどろどろに落ち込んだ時にだけ思い出す。はっきりカタをつけなければいけない時期だった。これ以上由実子という存在にこだわる必要などないのではないか。この結婚は間違いだったと認めることが最も素直な答えなのだ。由実子と別れる。片岡の生活の中から由実子の存在がなくなる。それがどんなに気分を晴らしてくれることだろう。しかしその一方で、由実子と別れることが最良の方法なのかどうか、片岡にはわからなかった。
片岡の両親は、片岡が小学生の頃に離婚した。母親が片岡を引き取り、大学入学までを女手一つで育てた。父親は離婚後すぐに別の女性と再婚している。二人の離婚の原因は父親の女癖の悪さだろうと片岡は思っている。
「あんな男と出会いさえしなかったら……」
「あんな男のようには絶対なるんじゃないよ」
夜遅く仕事から帰ってきた母親と薄暗い部屋で食事をとっている時、片岡がしばしば聞かされた言葉だった。離婚後の母親は仕事と片岡の教育だけに没頭した。
母親と二人で暮らし始めてから、片岡は五度父親と会った。回数を正確に覚えているのは、それぞれが片岡の人生にとって区切りの時期にあたっていたからだった。一度目は、両親の離婚後半年ほど経った頃だった。その時は母親に連れられて父親に会った。母親が父親をにらむように見ていた様子に寂しさを感じたのを覚えている。この時が三人で会った最後だった。二度目は中学校入学の時、三度目は高校入学の時、四度目は大学入学の時だった。片岡の進路が決まるたびに、母親はその報告をさせていた。会うたびに父親は違う女性と暮らしていた。五度目に父親に会ったのは母親の葬儀の時だった。参列者は十数人という形だけの式だった。母親は片岡以外には一切の感情を閉ざしたまま一生を終えた。父親のようにはなるな、斎場の待合で母親の叫び声が確かに片岡には聞こえた。今、父親が誰と暮らしているのか片岡は知らない。
由実子と別れさえすれば、すべてが解決するんだろうか。離婚するということは、さらに二人が深く傷つけあうということにつながるんじゃないのか。片岡の心は沈んでいくばかりだ。自分を苦しめる存在は切ってしまえばそれでいいのか?
切断された秋山の手首がずるずるとはいずりまわっている光景が片岡の脳裏に浮かんだ。由実子は手首なのか。片岡は自分の妄想に吐き気を覚えた。
*
看護師の持ってきたレントゲン写真は、案の定何の異常も示してはいなかった。念のために行った神経系の検査にもやはり異常は認められなかった。今の秋山に必要な手当ては左手の裂傷と火傷の治療である。これまでに秋山を診察した他の医者たちと同様にこのまま秋山を追い返すか、それとも精神科の診察を勧めるか、片岡は決めかねている。ただ、秋山の要望を聞きいれられないことだけははっきりとしていた。
秋山の精神はどこまで病んでいるのだろう。自分の身体を傷つけることで周囲の関心を惹こうとする症状を示す者は確かにいるが、ここまで自分を傷つけられるだろうか。秋山は本当に狂っているんだろうか。片岡はまだ迷い続けている。
「お願いですから、この左手を切り落としてください。どうして異常がなければ切り落とせないのですか、先生。手首の持ち主である私がこんなに頼んでも駄目なのですか。安楽死でさえ本人の意思があれば可能とされる時代ではないですか」
秋山は片岡から考える余裕を奪うかのように話し続ける。どれほど懇願されても、正常な手を切断するなどということが許されるはずがない。もしそれが許されるなら、お願いだから自分を殺してくれという自殺願望者がどっと病院へやってくるようになるだろう。
「どこへ行っても、答えは同じでした。健康体であるものを切断することは医者としてできない。どの先生も同じことをおっしゃいました。でも先生、例えば老婆の役作りのために健康な歯を抜いてしまった女優さんがいましたが、あれはどうなりますか」
秋山は自分の感情を抑え切れなくなってきていた。眼窩の奥の瞳が鈍く光る。
「親の腎臓を子供に移植するのはどうですか。移植を受ける方は、もちろん医療行為になりますが、腎臓を摘出される方には何のメリットもありません。健康な腎臓を切り取るのです。人を救うためなら許されるのですか。私の左手は誰も救うことが出来ないから切り落とせないのですか。どなたにでも差し上げます。正常な手なら誰かの役に立つのではありませんか。私の仕事は髪の毛を切ることでした。痛みを感じない部分なら切り落としても構わないのですか。爪を切ることはどうです。どれも同じ人間の身体ではないですか」
秋山は医療とは何かということを問いただしているのかもしれない。おそらく何人もの医者に手首の切断を断られた経験から、なんとか医者を説得する糸口を見つけようと必死で考えてきたのだろう。
医者とはいえ、すべての分野に精通している訳ではない。かと言って、ここでボロをだせば秋山に突っ込まれてしまう。次々に質問を繰り出す秋山の前で、片岡はどう返せばいいのかと、慎重に言葉を選ぶうちに答えるきっかけを失ってしまっていた。と言うより、言葉が思い浮かばなかった。むしろ何もかも秋山の言う通りではないか。そう片岡は考え始めていた。
医療の第一の目的は病気や怪我による身体的苦痛を取り除くことにあるはずだ。秋山の左手は医学的には何の異常もみられない。苦痛など存在するはずがない。苦痛は秋山の生み出した幻なのだ。この場合、手首を切断することよりも、それを切断したいと考えている秋山の精神面のケアが最も大切なことなのだ。彼の左手は救われなければならないし、治療を受けるべきは秋山の精神である。でも、果たして本当にそうなのだろうか。片岡は自分の考えに自信が持てなかった。
片岡の脳裏に由実子のことがまた浮かんできた。
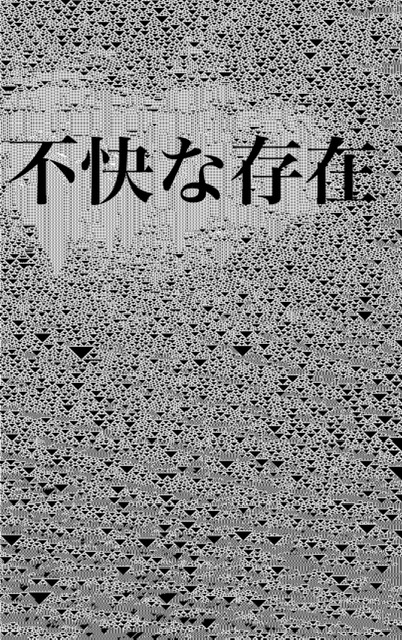
よければtwitterものぞいてみてくださいね。山猫 (@keystoneforest) | Twitter

山猫🐾@森の奥へ