連載3回目です。1回目、2回目はこちら👇です。
秋山の話を聞いているうちに、診察室の空気も重くなったように片岡には思えてきた。少し息苦しくなった気もする。どろどろとした話の展開に片岡は口をはさむことが出来ないでいた。話題にされているその左手は、秋山の話す間ずっとふらふらと気味の悪い動きを続けている。片岡の目はその動きをぼんやりと追っているだけだった。
*
そして二カ月前のある日、秋山は突然左手の自由を失った。動くには動くが、秋山の意思とは関係のない動きしか出来ないようになったのだ。
手を洗った後いつもするように、その臭いを嗅ごうと左手を鼻に当てる動作をしかけた途端、左手はぶるぶると震えるばかりで思う通りには動かなくなってしまった。指先だけが何かを掴もうとするように小刻みに動く。そしてそれまでに感じたことのない異様な感覚が左手を襲った。しびれたような、かゆいような、痛いような、とにかくとてもじっとしてなどおられない変な感覚だった。秋山は左手だけが別の生き物になったように感じた。試しに人差し指を動かそうとしてみたが、人差し指どころか手首自体が思うように動いてはくれない。左手に意識を集中すれば集中するほど、変な感覚はより強くなっていく。左手だけが金縛りにあったような気分だった。息が詰まりそうになる。
秋山は右手で左手を思いっきり掴み、左の手のひらを無理矢理開かせた。右手の親指の腹で必死に左の手のひらをさすった。引っ掻いてもみた。やがてじっとりと左手に汗がにじんできた。そして、またあの嫌な臭いが漂ってきた。洗面台へ走って水道の蛇口を思いっきりひねり、左手首を水流に浸した。でも、何も感じなかった。
数分して? 数十分して? ようやく、ぼんやりしていた水圧と水の冷たさが感じられるようになってきた。しばらくそのまま水を流し続けた。肩にのしかかっていた重しが少しずつ緩んでいくように思えた。ドクドクと腕に送り込まれていく温かい血流を秋山は感じた。そしてやっと、手の不快感は薄らいでいった。
が、それ以来時折、左手は勝手に踊りだすようになった。
手が臭うだけならまだ仕事は出来た。けれど、手の自由が効かなくなると、もうどうしようもない。初めのうちこそ水で冷やせば治っていたが、すぐにそれは効果をあげなくなった。不快感を紛らすには、それ以上の痛みを左手に与えることくらいしかなかった。眠っている時にもそれは秋山を襲った。手の不快感と痛みで目を覚ますと、知らず知らず右手で左手を掻きむしっていたこともしばしばだった。右手の爪が左の手のひらや甲に食い込んで赤い筋を無数に刻み、爪の間には剥ぎ取られた皮膚がごっそりとはさまっていた。そして、痛みが治まればまたあのおぞましい感覚が甦ってくる。
*
「、、、眠れない夜ほど長く感じられるものはありません。そして睡眠不足のままで仕事をするときほど長く感じられる昼もありません。私には休める時間が一切ありませんでした。左手が思うように動かず、意識も朦朧としてきます。とうとう私の中で何かが切れてしまいました。不快感が私を襲うたびに仕返しに左手を責めました。引っ掻いたり、切りつけたり、ライターであぶってみたこともありました」
秋山は全身を小刻みに震わせ始めた。身体の中からたぎり出す嗚咽を抑え切れなくなったようだ。歯を力一杯食いしばっている。
「手を見せていただけますか」
これ以上続けさせておくと、何を言い出すか分からない。片岡はようやく声をかけることが出来た。まず肝心の手袋の中のその左手を診なければならない。
「じゃあ先生、これを外すのを手伝っていただけますか。普通の手袋だと臭いを止められないのでこんなものを使っていますが、外すのがなかなか大変なのです」
秋山は自分の左手首を右手で掴んで片岡を誘った。片岡は手袋に両手をかけて慎重に引っ張った。少し力を入れると、手袋はずるりと脱げた。
その手を見た瞬間、片岡は言葉を失った。そして秋山の話にはたった一分の嘘も混ざっていなかったことを確認した。それは手というより、ただの肉塊だった。ボロ雑巾のように爛れていた。真皮にまで達している引っ掻き傷とカサブタが左手の表にも裏にもびっしりとこびりついている。薄黒く変色している部分は火傷の跡なのだろう。右手の倍ほどに腫れ上がり、傷が膿んでいるらしく異様な臭いが漂っていた。片岡は作り物の腕に似た何かがそこにくっつけてあるような違和感を覚えた。それは秋山の表情があまりに平然としているからかもしれないし、生きている人間の身体の一部だと認めるのがためらわれるほどひどく傷んでいるからかもしれなかった。
「ひどいものでしょう。今朝もこの手がざわざわと不快だったので、引っ掻いてしまいました」
秋山が右手を離すと手首はだらりと力なく垂れ下がった。
「痛みは普通に感じるんでしょう?」
片岡の質問に秋山は軽く頷いて、少しだけ左目をしかめて見せた。傷の具合からすると、焼けるようなジリジリとした痛みが秋山を責め立てているはずだ。
「悲鳴をあげたくなるほど痛みます。でも、この方が楽なのです。あの苛々する感覚よりは、よほど」
今はこの痛みのせいで落ち着いていられるのです、と秋山は言葉を続けた。
「先月、とうとう店を閉じました。この左手はもうまったく言うことをききません。それどころか、この左手があるせいで私は夜も寝られないし、ほっと息をつくこともできません。家内は気味悪がって家を出て行ってしまいました。この左手は私の身体から栄養分を吸い取る寄生虫のような存在で、私を苦しめるためだけに生きているのです。確かに私の身体にくっついてはいますが、私の意思が伝わらないまったく別の生き物なのです。わかっていただけますか、先生」
最後の「先生」は秋山の祈りの言葉のように聞こえた。
片岡には考えを整理する時間が必要だった。おそらく何人もの医者に相談したという秋山の言葉に嘘はないだろう。そして、検査の結果何も異常が見つからなかったという言葉にも。このひどい症状にも関わらず、検査に何も異常が発見されないとなると、秋山の精神の方に異常があると考えるほうが妥当だろう。しかしとにかく、片岡には考える時間が必要だった。看護師に秋山の手の治療とレントゲン撮影とを頼んだ。その間に順番を待っている残りの患者の診察を先に済ませてしまっておかなければならない。秋山の診察にいつまでかかるか見当もつかなかった。もうすでに一時間以上秋山の話は続いている。
残りの患者の診察を終え、時刻を確かめようとして、片岡は由実子とのことをふと思い出した。
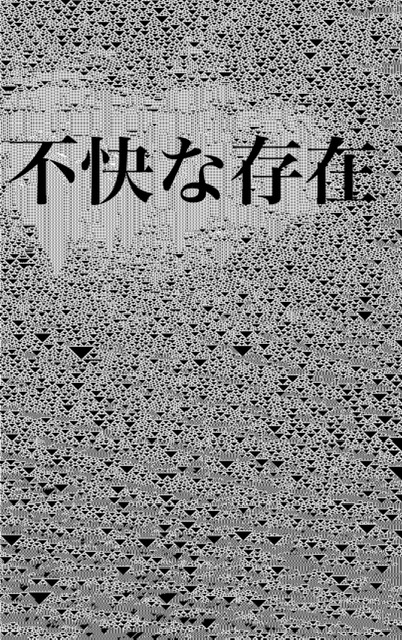
よければtwitterものぞいてみてくださいね。山猫 (@keystoneforest) | Twitter

山猫🐾@森の奥へ