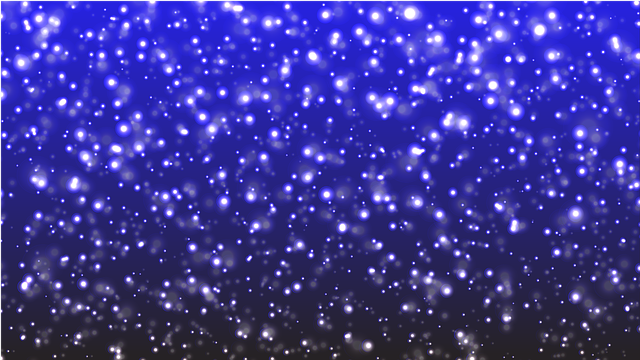※今回の創作は原稿用紙にすると40枚弱、文字数だけでは1万2千字ほどになります。これまで1記事につき数千字くらいまでの分量を目安にしてきましたので、どういう形でアップすればいいのか、少し悩みました。いえ、大げさに言いました。少し考えたくらいでした。で、話の区切りがよさそうなところで分けて、5回分でアップすることを考えました。起・承・承・転・結、みたいな構成です。回ごとに文字数が異なり、分割することで、拙い作品がさらに読みづらくなることがあるかと思いますが、お気づきのことがあればアドバイスください。よろしくお願いします。
1回目は、こちらです。
今回は2回目、承その1、です(^^;
空知らぬ風
年が改まった。医者に診てもらってからすでに三月目に入っていた。
あと少し働けば、借りも返してしまえる。
けれど、咲の容態は芳しくない。血を吐く頻度が日に日に増してきていた。
村に、年が明けて初めての雪が舞った。
咲はもう三日ばかり高熱にうなされつづけ、意識が戻らないでいる。
頬はこけ落ち、窪んだ眼窩を縁取る翳りが痛々しかった。
眠りどおしだった咲は、その間、正吉が無理に口に流し込んだ粥を少しとっただけだ。
嫌な夢ばかり見るのか、喘ぐような息をしながら、幾度もうなされていた。
正吉さん……。
ひどく咳き込んだ後で、咲は意外なほど大きな声で正吉の名を口にした。
正吉は寝言かと思い、咲の額に乗せた手拭いを新しく絞ったものに取り替えようとした。
その時、不意に咲が目を開けた。
「正吉さん? そこにおいでですか」
咲の瞳はまっすぐに正吉の目をとらえた。
吸い込まれそうだ、と正吉は思った。
生気のない咲の顔で、そこだけが異様なほど深い輝きをたたえていた。
「ああ、いるよ。咲、私はここにいるよ」
「よかった……」
深く吐息をついて、咲はつづけた。
「咲は、夢を見ておりました。次の春の卯月八日の花祭りの夢です」
「おお、桜餅を食い過ぎた夢でも見たか」
正吉が混ぜっ返す。
「正吉さん、よしてください。いつまでも子供扱いしないで……」
「……次にその日が来れば、咲は二十二になります……」
「……正吉さんは、お祝いに両手に抱えきれないほどの野の花を集めてきてくださいました……」
「……卯の花、菜の花、仏の座。山吹、蒲公英、桜草……」
咲は指折り数えながら、遠い昔のことを思い出すような顔で言う。
「咲は、お花の山にうずもれてしまいそうでした。どこで摘んでこられたのか、お尋ねしても、正吉さんは何もおっしゃいません。静かに笑っておられるだけでした。咲は正吉さんのその笑顔が大好きでした。それからしばらく、二人でお花を見ていました。……けれど、不思議なことがありました。あんなにたくさんのお花が、少しも匂ってまいりません。それだけではありません。『正吉さん』とお呼びしても、声が届かないようです。何度お呼びしても、一向に気づいてもらえません。よく見れば、正吉さんのお口が動いていて、何かおっしゃっているようなのです。ですが今度は、一言も咲には聞こえてまいりません。咲の耳が聞こえなくなってしまったのかと、最初は思いました。でも、そうではないようです。それで……、分かりました。咲は音のしないところにいるのです。……溢れるほどのお花、ありがとうございました。夢の中で咲が申したかったのは、お花のお礼でした。咲にはもうそれだけで充分です。本当にありがとうございました。でも……、その次からは、咲のことなどお忘れください」
真剣な表情でそんなことを言うものだから、正吉は咲が何の話をしているのか、まるで意味が分からなくなってしまった。
意識が乱れはじめたのではないか、そんな思いが頭をよぎった。
それを打ち消すように、正吉は明るい声で咲に話しかけた。
「夢の中でしたことに礼など言うな。そんなことより、どうだい気分は? 顔色がずいぶんよくなったね。これだけ話せるようになれば、大丈夫、もう大丈夫だ。峠は越した」
「いつまでも……、難儀ばかりおかけします」
「ああ、難儀難儀。でも、まあいいさ。気にするな、咲。のどが渇いたろう、これをお飲みなさい」
正吉は言いながら、湯飲み茶碗を咲の前に差し出す。
一口飲むと、咲はとろけそうな笑顔になった。
白湯の上に薄紅色をした小さなものが浮かんでいる。
塩漬けにされていたそれは、湯に浸されて気持ちよさそうに五枚の花びらを広げていた。
「良い薫りがいたします」
咲は横になったまま、頭だけ正吉の方にもたげて、ゆっくりとそれを飲み干した。
その様子を見て、正吉は何度も大きくうなずいてみせた。
「うまいだろう? 咲の大好きな桜湯だ。草右衛門の家で作っていたのをもらってきた」
正吉は目を細めて、うれしそうに咲の表情を見つめている。
そのくせ、今にも咲が弱気なことを言い出すのではないかと不安だった。
その隙をつくりたくなくて、言葉を継いでいく。
「いつまでも家の中にいてばかりでは気が滅入る。ほら、見てごらん。外は雪だ」
正吉は着ていた綿入れを脱いで咲に羽織らせると、戸を少し引いた。
開いた隙間から冷気が流れ込んでくる。
地面にはすでに白いものがうっすらと積もっていた。
陽は雲に隠れて見えない。
閉め切った部屋にずっといた二人には、それでも眩しいほど外は明るく見えた。
肌を刺す冷えた空気の中を粉雪がひらりひらりと落ちてくる。
風はやんでいるようだ。
二人は肩と肩を寄せて、しばらく何も言わずにそれを眺めていた。
「散っていくように見えます」
ぽつりと咲が言った。
正吉はその言葉に不吉なものを覚えて、とっさに何も返せなかった。
「咲が生まれたのは、卯月八日の花祭りの日の朝でした。父は咲が生まれてくるのを待ちながら、庭の桜を見ていたそうです。するとそちらの方で、きらりと光るものが見え、それと重なるように咲の産声が聞こえてきたのだそうです」
卯月八日、旧暦の四月八日は釈迦の生まれた日とされ、灌仏会(かんぶつえ)という、仏像に甘茶を灌ぐ法会が催される。
民間の行事としては、この日を花祭りとか、花の日とか称し、庶民は野や山、磯辺に出かけ、皆で飲食を共にした。
「光は、咲きはじめた蕾の内側から差してきたと、父は譲りませんでした。けれど、母はついにその話を本気にしないままでした」
「ああ、そうだった。だからお前は『咲』と名付けられた」
正吉の言葉に咲は頷いて、後をつづける。
「その日は、穏やかに風が流れる暖かな日で、一つ目の蕾が開いたのにつづいて、星が瞬くようにあちらこちらで光が見えた。そして、次々にどの枝の花も咲きはじめ、見る間に桜の木々が満開になってしまった……。そんな戯れ言のようなことを父は申しておりました」
「咲、もうあまりしゃべるな。身体に毒だ」
それは、正吉も何度か聞かされた話だった。
少し自慢気に話す義父の顔が目に浮かぶ。
けれど、その義父も義母もすでに亡く、確かめる術はない。
咲はどうしてこんな話を今さらながら私にするのだ?
正吉はその先を聞くのがためらわれた。
二人が一緒になってから、まだ数年しか経っていなかった。
赤子もまだない。
夫婦の契りを交わしたのは、咲が生まれた日と同じ花祭りの日だった。
二人で野に出かけ、満開の桜の花の下で、白い米の握り飯をいくつも食べた。
あの日も本当にいい天気だった。
たったそれだけのことが、今日までで一番の贅沢だった……。
振り返れば、二人で共にできたことよりも、できなかったことばかりが浮かんでくる。
「でも、花はいつか散ります。咲は……、もう長くはないのでしょう?」
咲の声が低くなった。
正吉の方を見ずに言う。
「そんなことがあるものか。じきに治る。気弱を言うな」
「いえ、咲は少しも怖くはありません。けれど、正吉さんの笑顔が見られなくなってしまうことだけが、悔しくて……。ですから……」
咲は咳き込みながら、それでも途切れ途切れに言葉をつづけようとする。
正吉は咲の肩を優しく抱きしめて言う。
「いつだって笑顔くらい見せてあげる。お前を一人になどするものか。いつまでも一緒だ。だから、さあ、もうお休み」
咲はまだ何か言いたそうな表情をしていた。
でも結局、それきりで言葉を切ってしまった。
その先を、咲は何とつづけようとしていたのか、正吉にはついに訊き返す機会は巡ってこなかった。
雪はその日から何日も降りつづけ、村は雪に閉ざされた。
咲の容態は悪くなる一方だった。
咳がおさまらず、充分に眠ることすらできなくなった。
咲は彼岸との境をさまよいながら、また夢を見た。
――春の日射しが降り注いでいる、花祭りの日。
蝶や蜂は蜜を集めるのに忙しい。
抜けるような青い空には、綿雲が二つ、三つ、のんびりと浮かんでいる。
彼らに誘われて、咲の身体が弾みだす。
少しも重さを感じない。
咲はしだいに高く昇っていく。
雲に手が届きそう。
咲は思いっきり手を伸ばす。
あと少し、というところで雲は不意に先へ流れる。
もう一度手を伸ばす。
また雲は逃げる。
すぐそこにあるのに届かない。
髪留めが緩んで、咲の長い黒髪がはらりと解ける。
髪も雲の後を追いかける。
下方から桜の花びらがふわり舞い上がってくる。
風が、咲の隣にいた。
すべては風の仕業だった。姿は見えないけれど、ずっと前から風はそこに吹いていた。
咲は風に身を任せる。
すると、咲はまたさらに高く昇っていった。
そして身体中の痛みが薄らいでいく。
風になりたい……。
咲は思った。
眼下には咲の暮らした村が見える。
正吉が花盛りの野にござを敷いて座っている。
もうずいぶん小さくなってしまったけれど、正吉の顔は一目で見分けることができる。
正吉が笑った。
その笑顔に触れると、咲の身体に温かいものが満ち溢れる。
けれど笑い声が聞こえない。
咲の耳には何も響いてこない。
そして正吉は、咲の知らない誰かに向かって、笑いかけている。
正吉を囲んで笑いの輪が広がっていく。
みんな笑っている。
なんて楽しそう……。
ねえ、正吉さん。何がそんなに楽しいの?
咲も笑ってみる。
でも、その声は正吉には届かない――
「正吉さん……」
本当は忘れないで欲しい。
せめて花祭りの日一日だけでも、咲のことを想っていて欲しい。
咲の意識は、最期にほんの一瞬だけ正吉の傍に舞い戻ってくる。
苦しい息の下で咲は思いの丈を言葉にした、つもりだった。
けれど、正吉は少しも気づかない。